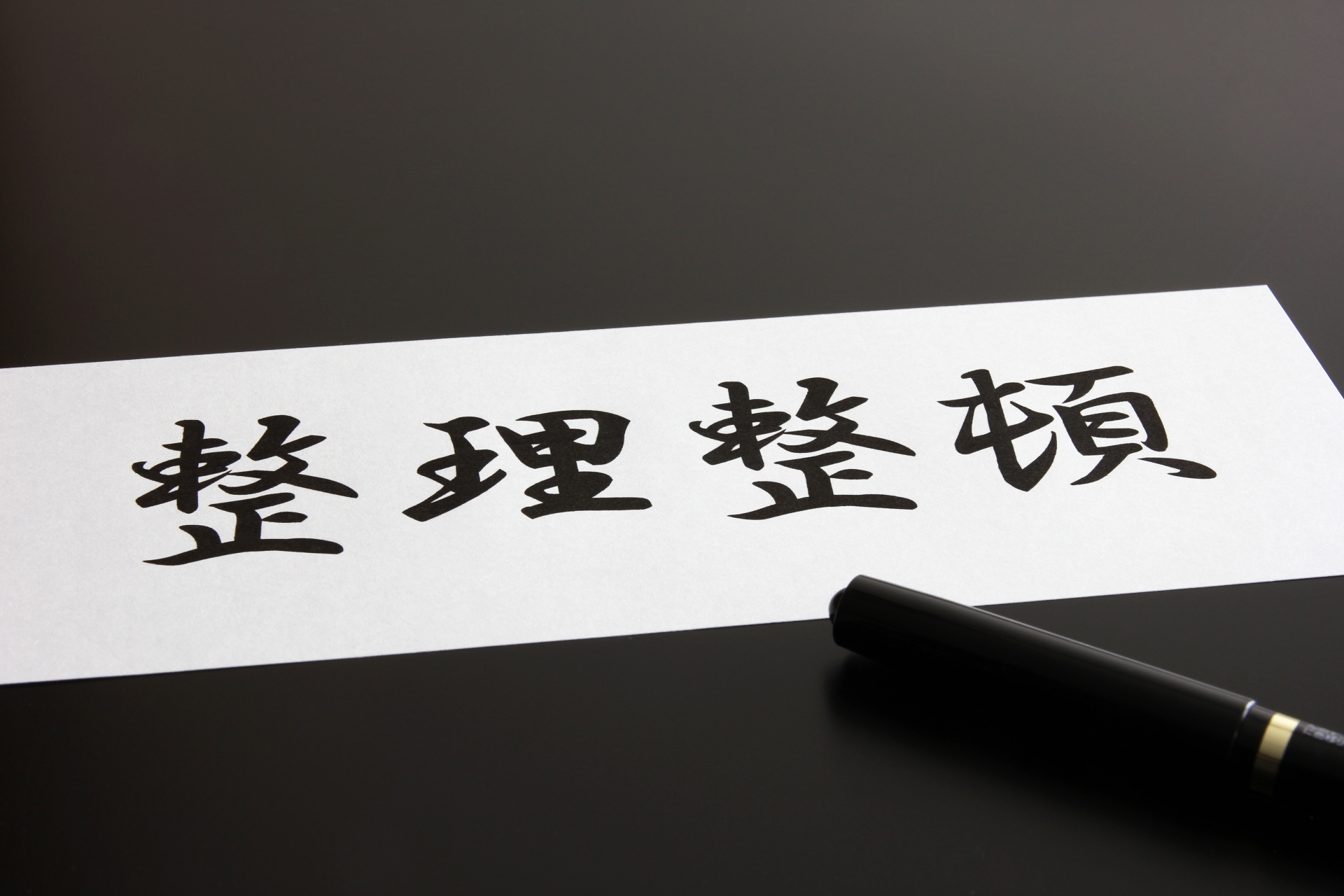こんにちは。
そうじで組織と人を磨く、日本で唯一の研修会社 株式会社そうじの力
代表取締役・組織変革プロデューサーの小早祥一郎です。
世の中、「5S」「環境整備」などに活動に取り組んでいる会社は、決して少なくありません。
しかしながら、そのすべてが「期待するような効果」を上げているわけではないようです。
「やってみたけれど、うまくいかなかった」
「一過性で終わってしまった」
「続けてはいるけれど、マンネリ化してしまっている」
…
「期待するような効果」を上げられない理由は、一体何なのでしょうか?
その理由を解き明かすのが、本シリーズコラム。
全10回にわたってお伝えしていきます。
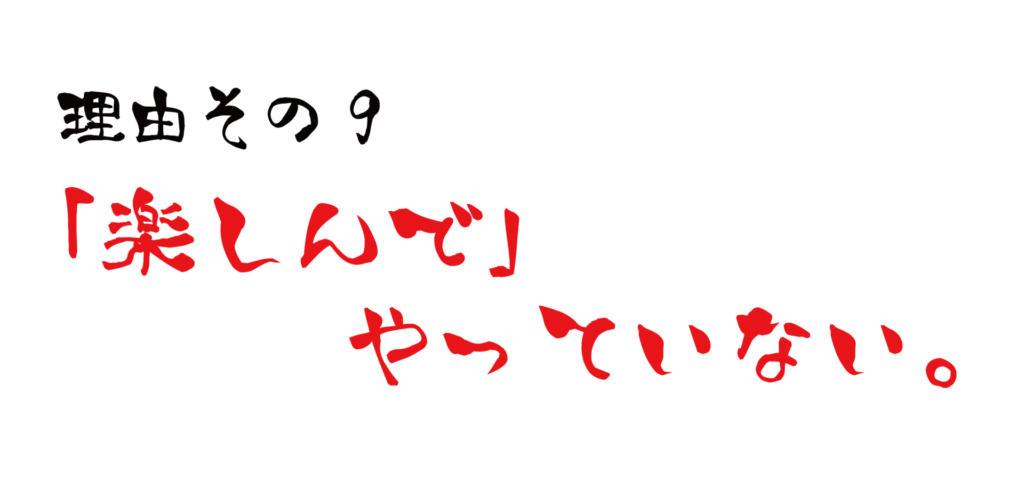
「社内見直しポイント」が確認できる!
社長のための環境整備チェックシート、無料公開中!
⇒ダウンロードはこちら
目次
「ダメ出し」ではなく「ネタ探し」
そうじ(環境整備)の活動は、意識しないとどうしても「ダメ出し」モードになりがちです。
なぜならば、活動そのものが「状態を正すこと」。
つまり、乱れていたり汚れていたりと、「できていないこと」に目が行くからです。
確かに、乱れていたり汚れていたりするものを放置しておくわけにはいきません。
ただ、
「これがダメ」
「あれもダメ」
と言われてばかりいれば、自分自身を否定されている気がしてしまうもの。
指摘される方は嫌になってしまいます。
人間、やらなくてはいけないと頭では理解していても、楽しくないことは続かないものです。
では、どうすれば良いのでしょうか。
発想の転換です。
乱れや汚れを「欠点」とみなすのではなく、改善の「ネタ」だと捉えるのです。
汚れや乱れには、「原因」があります。
というよりも、汚れや乱れは、その原因が「目に見える形で出ている」だけに過ぎません。
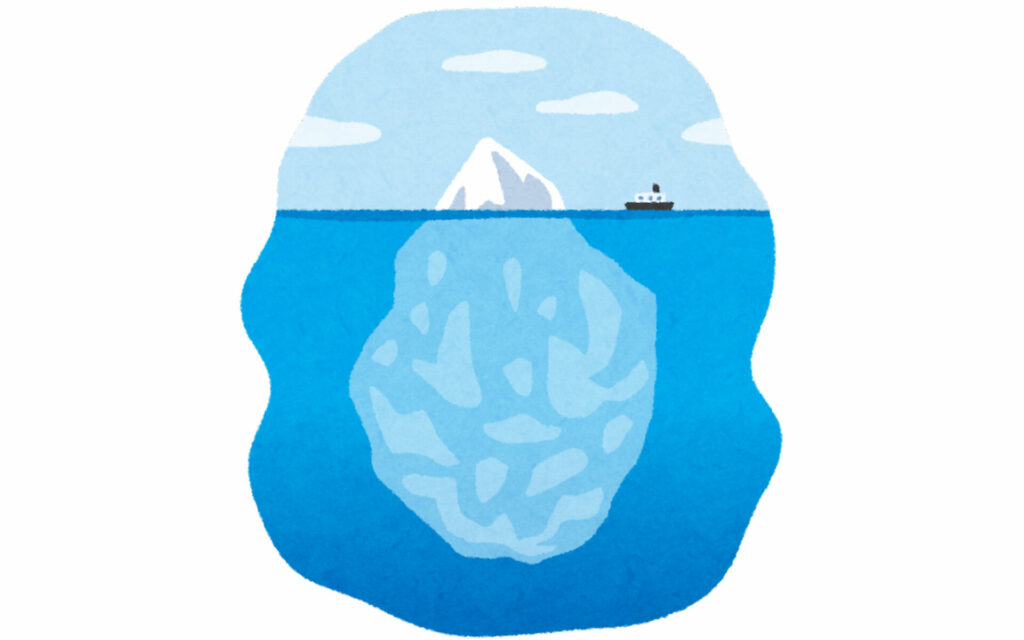
大切なのは、その原因を探り、再発防止策を打つこと。
本質的な問題に切り込み、解決することです。
「ネタ」があるからこそ、原因にアプローチすることができるわけです。
それに、最初から整っていたら、やることがなくてつまらないでしょう。
だから、ネタは多ければ多い方が良いのです。
ビフォア・アフターの写真だって、ビフォアがひどければひどいほど、アフターが映えますよね(笑)。
だから、工場や倉庫、社内を巡回するのは、「ダメ出し」ではなく「ネタ探し」。
個人のアラ探しではなく、組織の機能不完全な部分を探す取り組みであることを、理解してもらいましょう。
楽しさの第一は「皆でやること」
では、「楽しさ」とはいったいどんなところから生まれてくるのでしょうか?
組織の中には、いろいろな性格の人がいて、いろいろな考え方の人がいます。
なので、なかなか唯一の正解というのは導き出しにくいです。
ただ、私が多くの事例を見てきた中で感じるのは、
「社長以下みんなで一緒に活動すると、自然とみんな笑顔になる」
ということです。

たとえば洗車。
洗車って面倒ですよね。
一人でやると、だいたい1時間くらいはかかります。
体力的にもキツイです。
でも、3人くらいでやると、これがとても楽しいレクリエーションに変わります。

複数人で洗車すると、普段自分では気づかない汚れに他人が気づいてくれて、
「ああ、こんなところも汚れるんだな」
という新たな発見があります。
今までなかなか落とすことができなかった頑固なホイールの黒ずみ。
これも皆でゴシゴシやることで、
「うわっ、結構落ちるね!」とか
「もっとこうした方がキレイになるんじゃないか」
とか言いながら、和気あいあいと進めることができます。

何より、皆でやれば時間も短く済みます。
終わった後にアイスを食べたりすれば、そこでまた会話も生まれることでしょう。
「そうじは黙ってやるもの」
「そうじは修行」
と考える経営者もいます。
社長自身が、その「修行」を心から楽しんでやっているのであれば別として、よほどでない限り、その中に「楽しさ」を見出すのは難しいこと。
残念ながら、それではほとんどの社員はついてこないでしょう。
作り笑顔はどこかでボロが出る
中には、アメとムチ的な賞罰規定を設けて、強制的に環境整備をさせる会社もあります。
ある会社の朝礼や環境整備を見た時に、その一糸乱れぬ所作に圧倒されました。
驚いたことに、社員の皆さんの顔がまた、一糸乱れぬ笑顔なのです。
しかし私には、それは不自然な作り笑顔に見えました。
もしこの会社で、賞罰規定がなくなったら、どうなるのでしょうか?
もし環境整備チェックを行う社長がいなくなったら、どうなるのでしょうか?
きっとその作り笑顔は崩れてしまうでしょう。
環境整備も、おざなりになるでしょう。
でも世の中には、正反対の会社もあります。
社長が事故で怪我を負い、一年半も不在だったある小さな会社。
事故のずっと前から、社長から率先してそうじ(整理整頓)に取り組み続けていました。
社長が不在の間も、社長の想いを受け継ぎ、社員たちは工夫して、そうじに取り組み続けました。
「おたくももう駄目だね」と他社から言われたこの会社は、なんとその年、過去最高売上を上げたのです。
強制力だけでは、このようなことは実現しえないでしょう。
「皆で一緒にそうじをすることが楽しい」
という状態を普段から作り上げていくことが大切です。
まとめ
私たちの定義するそうじとは、【本質を明らかにし、究めること】。
モノにアプローチしながら、実はそこにまつわるコトの問題をあぶり出し、改善していくアプローチなのです。
強制力を働かせることで、物理環境は整うかもしれません。
それによって、事故や怪我が減ったり、効率が上がったりといった、一定の効果も期待はできます。
しかし、強制力によってでは、自ら創意工夫したり、提案したり発展させることはできません。
まして、モノの改善に留まらず、そこにまつわるコトの問題に切り込んでいくことなど、到底できないでしょう。
強制力によらず、社員が自らそうじに取り組むためには、「楽しさ」が不可欠です。
実際、弊社の支援先でも、楽しく活動している会社ほど長続きし、大きな効果を上げています。

「5Sに取り組んでいるのにあなたの会社が変わらない10の理由」目次
その1 「社長がやらない」
その2 「組織を作らない」
その3 「時間を確保しない」
その4 「現場の取り組みだと思っている」
その5 「『モノ』へのアプローチにとどまっている」
その6 「リアクションがない」
その7 「目的を取り違えている」
その8 「経営計画書に明記していない」
その9 「楽しくやっていない」 ←本記事
その10 「社長が約束を守らない」
わたしたちは、”そうじ”で組織と人を磨く、日本で唯一の研修会社です。
◆社内が乱雑なことにお悩みの経営者様
◆環境整備を導入したいが、どうやって進めていけばいいのかお悩みの経営者様
◆他社の環境整備研修プログラムが、自社にはうまくはまらなかった経営者様
どうぞお気軽にご相談ください。
わたしたちは、
”そうじ”で組織と人を磨く、
日本で唯一の研修会社です。
◆社内が乱雑なことにお悩みの経営者様
◆環境整備を導入したいが、
どうやって進めていけばいいのか
お悩みの経営者様
◆他社の環境整備研修プログラムが、
自社にはうまくはまらなかった経営者様
どうぞお気軽にご相談ください。